凡庸な老人仲間が揃って「ヌード展」に。裸婦像を、見る眼イロエロ、ゾクゾクと
女性関係に疎い者同士(水戸一高校時代の同級生仲間4人)が、ボーっと生きてんじゃねーよ、とばかりに、「ヌード展」を見に行こうということになった。2018年の6月下旬、みなとみらいの横浜美術館で催されている「ヌード展」に、ロダンの刺激的な『接吻』が、日本初公開されているという。
横浜美術館に、ロダンの『接吻』が初公開
やはり、そこには大勢の人が押しかけていた。全裸の男女が熱く抱擁し、愛を確認し合っているかのような真っ白な大理石像は、生身の肌を思わせる瑞々しさで、自然に女性の柔らかい個性的な部分に眼がいってしまう。
その官能的というか、躍動感というのか、間近で見る抱擁の生命力に圧倒され、思わず隅っこの方の説明文に眼をやると、「イギリスから持ってきたこのロダンのコレクションは、いまから100年前の第1次世界大戦中、ロンドンで展示されたが、エロティックすぎるということで、胸から下部が布で覆われ公開中止となった」という。当時のロンドン市民にとっては、プロテスタントの禁欲的な倫理観が強かったのかどうかは知らないが、よほど、エロティックな作品と映ったのであろう。ロンドンにも腰巻事件があったのには、驚いた。
それにしても、この横浜のヌード展には、何もロダンの『接吻』ばかりでなく、ドガやルノアール、マティス、ボナール、ピカソといった20世紀前半の名だたる画家の最高傑作品がずらりと展示され、「横たわる裸婦」「浴室の裸婦」「布をまとう裸婦」「座る裸婦」「首飾りをした裸婦」といった作品名の裸婦像が130点余も展示されていた。ヌード展とはいえ、よくもハダカばかりを集めたものだ。
中には、眼のやり場に困るような強烈な自己主張をしている艶やかな肉体画もあり、老人仲間の血圧もかなり高くなったようで、とても一服の清涼剤どころではなく、退館したあと毒消しにと、隣の高さ300㍍もある横浜ランドマークタワーの展望台に登って、フーっと長時間息抜きをした。
静嘉堂美術館には、
黒田清輝の「腰巻事件」の裸婦像が展示!
横浜のヌード展にかなり刺激されたのも束の間、世田谷・二子玉川にある「静嘉堂文庫美術館」からの招待券が届いていた。今度は、明治の「腰巻事件」で有名な黒田清輝の『裸体婦人像』が展示されているというので、俄然色めき立ち、同じ老人仲間を誘って、そのあとの8月、真夏の異常な暑さもものともせずに、見に行った。
この展示会は、「明治からの贈り物――明治150年記念」と題した明治時代の絵画、工芸品等を展示していて、何が目玉なのかよくわからないような案内だったが、とにもかくにも腰巻事件の本物の裸体婦人像の絵が静嘉堂文庫の裏の倉庫に眠っていて、滅多に展示されることがないということを知っていたので、それが今回出品されるというので、見れる絶好のチャンスだと思った。
いざ入館してみると、なんとその入口に入った途端の最初のコーナーに、堂々と、黒田清輝のその裸婦像が飾ってあるではないか。しかもその脇のパネルには、ご丁寧にも、当時(明治34年=1901年)のいわゆる「腰巻事件」となった乳房から下の部分のすべてが、黒い布で覆われた新聞写真と掲載記事の動かぬ証拠が飾られていた。
さらに説明文を読むと、「黒田清輝はフランスから帰国後の明治34年、第6回白馬会に、わが国ヌードの先駆的なこの作品を出品しました。ところが展示では、公序良俗に反するとして下半身が黒い布で覆われてしまいました。これが日本の絵画史上有名な腰巻事件です。このため、その後引き取り手が誰もなく、三菱財閥の岩崎家が購入し、コンドル設計で有名な岩崎家高輪本邸(現在の品川「開東閣」)のビリヤード・ルーム(女人禁制だった)に飾られていました」といった大要が書いてありました。
その絵は、素人の僕らが今見ても美しく、正面から堂々と座っていて、股間部まで描かれていて(ヘアはなし)も、まったく劣情は催しませんが、当時の社会認識では、風俗を乱すとして大変な騒ぎになったのでしょう。
ところが当の黒田清輝本人は、この警察の“弾圧”に対して強く抵抗したそうで、「元来、裸体画は絵画に取り最も高尚に属するものであるが、世の分からず屋には、未だに解釈ができなくて困る。自ら言ふはおこがましいが、最も困難で最も巧拙の分かるる所の、腰部の関節に力を用いたつもりであるが、その肝腎な所に幕を張られた訳だ。」と、その掲載記事で語っている。黒田の怒りは、かなりのもので、その後もヌードを描くことはやめなかったそうだ。

黒田清輝の『裸体婦人像』(静嘉堂文庫美術館)
藤田嗣治は日本を捨て「乳白色の裸婦像」で、
パリ画壇のトップに!!
しかし皮肉なことに、その黒田が、東京美術学校(現・東京芸大)の教授をしていた時、学生だった藤田嗣治を全く評価しなかった、という話も興味深い。
美術評論家でもあるタレントの山田五郎(上智大・新聞学科卒の小生の後輩)によると、「当時、薩摩閥が政界で跋扈し、洋画界の世界にも薩摩藩出身の“黒田閥”ができていて、藤田は今でいう黒田の“いじめ”にあい、傷心の身で単身パリに留学した。その憤まんが、藤田をしてあの独特な乳白色の下地を作り出し、一連のすばらしい「乳白色の裸婦像」となって人気を呼び、一躍パリ画壇のトップの地位を占めた」という。その後、日本にも捨てられた藤田が、晩年はフランスに帰化し、洗礼も受けたというから、国際派の巨匠・藤田のくやしさが、よく理解できる。その晩年をパリ郊外で支えた夫人が、わが茨城県出身であったことが、昨年の11月3日、片田舎の小・中学校同窓会の帰途、「笠間日動美術館」に立ち寄り、「藤田嗣治と陽気な仲間たち」展を見て知った。
なお、蛇足だが、赤穂浪士事件で有名な筆頭家老・大石内蔵助(笠間藩家老として笠間で、生まれ育ったことを知っている人は少ない)の銅像が、その笠間日動美術館の隣に建設されていた(まだ完成されていなかった)のには、驚いた。
(2019.01.15掲載)

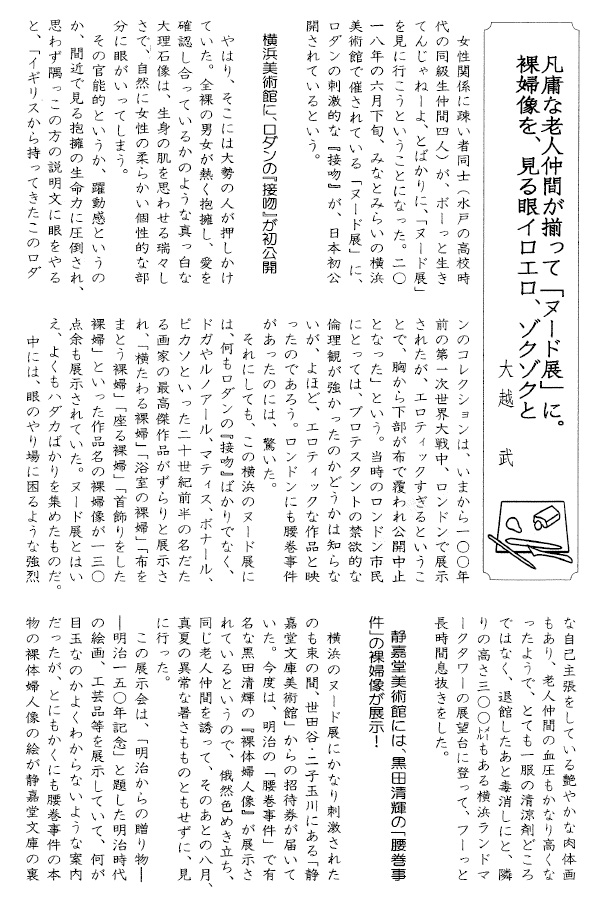

掲載:会報「サロン・ド・ムッシュ」2019.1月、冬号
|

